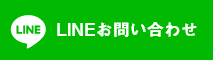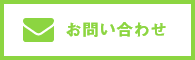-
平野
築30年の一戸建てにも資産価値がある?
皆さんは、築30年を超える古い一戸建ての正しい資産価値についてご存知でしょうか。手頃な価格の中古住宅を購入を検討中の方は、特に資産価値や商品価値に関心がありますよね。そこでこの記事では、築30年の一戸建ての資産価値と一戸建てを売却する際のポイントについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてみてください。 ■築30年の戸建に資産価値が見出される理由とは? まず1つ目の理由は、リノベーションが追い風になっているからです。20年ほど前までは中古の一戸建てを購入してリフォームする事例はほとんどありませんでした。多くの方は、新築を建てることに意識が向いていました。 しかし、10年ほど前からリノベーションの言葉が浸透して、人々に認知されていきました。建物は合う程度の悪い箇所があっても治せるという認識になってきたのです。古い家をカスタマイズすることで、新築と比較した際に工事費用を20〜25%程度縮減できるのです。それゆえ、その利点を活かす人たちが増えてきているのです。 2つ目の理由は、住宅ローン償還年数が見直されたことです。銀行の中古物件に対する担保評価が見直されたことが背景にあります。具体的には、「組めるローン返済年数」が見直されたのです。 20年前には中古物件を銀行ローンを利用して購入しようとした場合は、返済期間=25年−経過年数上記の式でローン返済変数が定められていました。当時は新築を建てるなら30年や35年の返済期間を組めました。それゆえ、多くの方が新築に移行していったのです。 ■築30年の戸建を売却する際のポイントとは? ここでは、売却時のポイントを3つ解説します。ぜひチェックしてみてください。 まず1つ目は、インスペクションをして安心を担保することです。売却前にインスペクションを実施することで、購入希望者に安心感を与えられます。 2つ目は、古家付き土地として売ることです。古い家が立っている土地を売却する際には、更地にした状態で売却する必要はありません。購入希望者の中には、リノベーション目的に方もいるため、そのまま売る方がメリットが大きいでしょう。 3つ目は、住宅ローンは完済することです。中古物件を売却する際には、住宅ローンを完済することが絶対条件になります。それゆえ、仮にローン残債が残っていても、売却代金から住宅ローン残高を一括返済できる状態なら住宅ローンの完済ができます。 -
平野
空き家の倒壊はだれの責任?
空き家が倒壊した際、誰が責任を負わなければいけないのでしょうか。放置していると、知らぬ間に倒壊していて賠償金が発生したと言うケースもあります。他人に被害が及ばないためにも、空き家はしっかりと管理しておかなければいけません。今回は、空き家倒壊時の責任の所在についてと、倒壊の回避の方法をご紹介します。 ■空家倒壊の責任の所在について 空き家管理は法律で定められているので、ケースによって誰に責任の所在が行くのかどうかは決まっています。通行人や隣人に被害が出た場合は、所有者が責任を負わなければいけません。これは民放717条で定められており、怠っている建物が倒壊して被害者が出た場合、空き家の管理を行っていなかったとみなされて、損害賠償責任を負う義務が生じます。 ◇空家等対策の推進に関する特別処置法 空き家の管理を怠り放置していると、空き家等対策の推進に関する特別処置法に基づいて、「特定空き家等」に認定されてしまいます。所有者には空き家を管理する義務があるので、管理を怠り続けると、行政代執行の危険性もあるので注意が必要です。 以下のいずれかに該当すると、特定空き家等に認定されます。・倒壊や保安上危険となる恐れのある状態・衛生上の有害が見られる状態・適切な管理を怠っていて景観を損なっている状態・その他の周辺環境の保全のため放置することが不適切である状態 ある日突然、行政代執行を告げられることはありませんが、その前に自治体からの命令や指導がある場合は、それに応じなければ行政代執行が行われるでしょう。 ■倒壊のリスクを回避する方法とは まずは、清掃作業が必要になります。庭の雑草処理や室内の換気、屋内と屋外両方の清掃が大切です。室内の清掃は、拭き掃除や水道のチェックで、特に水漏れしていないかも確認しておきましょう。外回りの清掃では、ゴミの掃除や建物に亀裂が入っていないかなども見ておきましょう。 最後に重要なのは、ご近所さんへの挨拶です。予め顔を合わせておくとトラブルにも巻き込まれにくく、近隣の方にとっても安心感があります。緊急連絡先として番号を伝えておくのも良いでしょう。 ■まとめ 空き家管理は法律で定められており、管理の義務を承知の上で所有しているとみなされるので、空き家を所有している方は責任を持って清掃や定期的な確認を心がけましょう。知らない間に倒壊していて、多額の賠償金を払わなければいけなくなったと言うことを防ぐためにも、きちんと管理しておくことが大切です。 -
平野
住宅ローンが残っている家の売却をしたい方へ!
何かの出来事を理由に家を売却したい方もいらっしゃるでしょう。1度家を購入してしまうと、ローンを返済し終わっていなければ家を売却できないのではないかと不安になりますよね。しかし、ローンが残っている家の売却方法はあります。今回は、住宅ローンが残っている家の売却方法をご紹介します。 ■住宅ローンが残っている場合について 住宅ローンの完済が終わっていなくても家は売れますが、その場合に確認することがあります。 まずは、住宅ローンの残高を確認しましょう。住宅ローンの残高は、償還予定表で確認でき、もし償還予定表が見つからなければ金融機関に連絡すると再発行してもらえます。残りの住宅ローンを手持ちのお金で払えるのであれば返してしまった方がスムーズに進められます。 次に、家がいくらで売れるかを確認しましょう。家の売却価格が住宅ローンを上回れば、住宅ローンを完済できます。周辺の似たような条件で売却されている物件を見てみると、ある程度参考になります。実際売却を検討されているお家の価値がどれくらいあるのか気になる方は、一度当社へご相談ください。 ■オーバーローンの家を売却する方法とは 売却資金よりもローンが多く残っている場合でも、家を売却できる方法が3つあります。 1つ目は、残りのローンを貯金や持っているお金で全て返してしまうことです。大金をすぐに用意できない場合は、家族や両親にお願いしてみる方法もあります。それが難しければ、金融機関から無担保ローンの査定を依頼できますが、審査が厳しくなってしまうため、あまりおすすめできません。 2つ目は、住み替えローンです。これは、買い替え時にローンを組む際、前回返しきれなかった分のローンをプラスアルファーで上乗せする仕組みです。しかし、借りる金額が大きくなってしまうので、上記と同様に査定が厳しくなります。住み替えローンのメリットとして、融資条件により前回のローンよりも低金利になる可能性があるのが特徴です。 3つ目は、任意売却です。これは、金融機関から特別な許可がおりた場合に家を売却できるというシステムです。金融機関がこのまま返済するのが難しいと判断した場合、任意売却が認められます。しかし、これは特例であり、ほとんどの場合は差し押さえの後に競売にかけられてしまいます。 ■まとめ 今回は、住宅ローンが残っている際の家の売却の方法をご紹介しました。ローンが払い終わっていないという理由で売却を諦めている方も多いですが、実は、家のローンが残っていながら家を売るという例は少なからずあります。住宅ローンの残っている家の売却について、詳しく知りたい方はぜひ当社までご相談ください。 -
平野
どっちが良いの?土地の相続と生前贈与を比較!
皆さんは、土地の相続と生前贈与のどちらが良いのかご存知でしょうか。土地をお持ちの方は、自分の死後に家族に相続してもらうべきか、生前贈与を先にしておくべきなのか迷いますよね。税金的にかかる費用を総合的に判断することが重要です。そこで今回は、土地の相続と生前猶予の違いとメリットについて解説します。 ■土地の相続と生前贈与の違いについて 相続とは、贈与者の死後に相続人で財産を分けることになります。また、生前贈与とは贈与者が生きているうちに財産を譲ることになります。両者の違いは、財産を渡す時期の違いです。 そして、生前贈与をした際には「贈与税」という税金を納めます。また、相続する際には、「相続税」を収めることになります。 生前贈与に課税される贈与税には「基礎控除」と言われる非課税枠が存在します。それゆえ、相続税対策には生前贈与が有効です。基礎控除は、財産をもらう人1人あたりに年間110万円が設定されています。よって、年間110万円以内の贈与は贈与税が課税されないのです。 ■土地の相続と生前贈与のそれぞれのメリットについて ◇土地の相続のメリット まず1つ目は、相続人によっては基礎控除に加えてさらなる控除も受けられることです。長年連れ添った配偶者が相続人となる場合に、「1億6千万円」と「配偶者の法定相続分相当額」の高い方が配偶者控除として認められる制度があります。これによって、一般的な住宅を配偶者が相続した場合は、多くの場合で非課税になると考えられます。 2つ目は、遺言者に詳細を記載する場合に相続のルールが明確で手続きが円滑であることです。遺言書に財産や分割方法を記載しておけば、トラブル回避できます。 ◇土地の生前贈与のメリット まず1つ目は、相続後のトラブルを避けられることです。相続でトラブルになりやすいのが財産分与になります。特に住宅のように分割が難しい財産には問題が起こりやすいですが、生前贈与であれば相続するかを被相続人が決めてその人に財産が譲渡されたか確認できます。 2つ目は、相続時精算課税を選択すると節税できることです。相続時精算課税は生前贈与を行う際の税金を一定額のみ贈与税として先納することで、残りを相続時に精算納税できる制度になります。贈与時の税負担を抑えて、確実に相続できます。 ■まとめ 今回は、土地の相続と生前猶予の違いとメリットについて解説しました。土地と生前贈与の違いは財産を譲渡するタイミングになります。また、それぞれのメリットを比較してどちらがよいか判断しましょう。この記事を参考にしていただけたら幸いです。 -
平野
空き家の維持費はどのくらいかかる?
「空き家にはどのくらいの費用がかかるのか」「両親が手放した空き家の処理の仕方が分からない」このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。 空き家は想像しているよりも高い費用がかかる可能性があるので、事前に対策をとることが大切です。今回は、空き家に必要な費用や整理方法をご紹介します。 ■空き家に必要な費用について 利用していなくても、空き家を所持するにはお金がかかります。固定資産税や都市計画税などの税金を払わなければいけません。土地面積や立地によって金額は変わりますが、空き家を放置し続けると固定資産税の負担が大きくなるので要注意です。 また、定期メンテナンスを使用する為、最低限の光熱費も必要です。空き家として放置する場合は負担を減らすために事前にプラン変更を検討しておくと良いでしょう。 建物は利用していないと腐食してしまう傾向があるので、定期的なメンテナンスを行うのが理想です。特に、水回りや壁、内装はコンスタントにメンテナンスを行う方が空き家の腐食を防げます。物件の状態によってメンテナンス費は変わるので初期修繕費用と定期修繕費用に分けて計算すると整理しやすいです。 建物を建てる際に加入必須な火災保険やその他の保険は、維持する際にも必要です。負担が少ない保険のプランに乗り換えることをおすすめします。 ■空き家の整理方法とは? 空き家はそのまま放置していると維持費がかかってしまい、メリットよりもデメリットの方が大きくなってしまうので、早いうちに対策を取るのが良いでしょう。維持できなくなってしまった空き家は、売却できます。しかし、時間が経って老朽化が進むと資産価値が減ってしまうので、早いうちに売却するのがおすすめです。 建物を解体して土地として利用するのも選択肢の1つです。土地を賃貸したり、売却したりできます。借主、買主が家を管理することもなくなるので、自分の土地を自由に使えます。 固定資産税や都市計画税の住宅用地の特例対象に入っている場合は、建物を解体した後は外れてしまうので注意しましょう。土地の固定資産税や都市計画税は高くなってしまいます。 ■まとめ 今回は、空き家の維持費についてご紹介しました。維持費に負担がかかってしまう場合は、売却や解体するなどの対処をできるだけとる必要があります。大切なご両親が残してくれた住宅や思い出の詰まった住宅は、後悔のない空き家処理を行いたいですよね。維持費や必要な費用は前もって把握しておきましょう。 -
平野
空き家を賃貸に出すメリットとデメリットとは?
現在所有している不動産を空き家のまま放置しているという方はいらっしゃいませんか。空き家として放置していても、毎年税金がかかってしまい勿体なく感じてしまうという方もいらっしゃるのではないのでしょうか。今回は、空き家賃貸経営のメリットとデメリットについてご紹介します。 ■空き家賃貸経営のメリットとは? 土地や建物を所有していると、毎年の固定資産税や都市計画税などの税金は付き物です。これは空き家として所有していても同じであり、空き家をうまく活用していない方にとっては勿体無いと言えます。そこで、空き家を有効活用する手段として賃貸経営という方法があり、家賃収入という新たなお金の稼ぎ方も生まれます。人気のある都心部や需要の高い土地であれば空室になることも少なく、長期的な利益も期待できます。 賃貸物件にする以外にも、今ある空き家を解体してコインランドリーやコインパーキングなど無人で経営できる手段もあります。しかし、解体費用や設備の管理費用がかかってしまうので、初期投資を行うというデメリットが伴います。それに比べ、空き家のリフォームは改修箇所が少なければ大規模な工事を行う必要がないので負担は軽減されるでしょう。 また、空き家対策法という特定空き家に指定されると、固定資産税が6倍になるというシステムがあります。空き家を所有しているだけで固定資産税や都市計画税が徴収されるにもかかわらず、税金が上がってしまうと勿体ないですよね。空き家で何かしらの賃貸経営を始めると、特定空き家指定を回避できるのでお勧めです。 ■空き家を賃貸で出すデメリットとは? 不動産の使用方法において近隣とのトラブルがあった場合に自分で処理しなければいけない点がデメリットとして挙げられます。さらに、修繕費や管理運営を行う上で発生する必然的な出費も避けられないでしょう。 入退去の際のクリーニングはもちろん、水回りや故障などの際には対応しなければいけません。人気のある地域に不動産をお持ちの方は心配無用かもしれませんが、入居者が見つからなければ家賃収入は滞る上に、次の入居者が見つかるまでは定期的に掃除しなければいけません。常に手入れをする必要があることは、やはりデメリットに当てはまるでしょう。 ■まとめ 空き家の地域によっても異なりますが、長期的に考えると空き家のまま放置するよりも賃貸経営をした方がメリットは大きい可能性もあります。現在空き家を所有している方は、空き家賃貸経営を考えてみてはいかがでしょうか。 -
平野
不動産の家の相続手続きに期限はある?
不動産の相続手続きには期限が設けられています。期限内に行わなければ、正式に契約ができなかったり、望む通りに進められなかったりすることもあります。相続は、きちんと手続きを終わらせたいですよね。今回は、不動産手続きの期限や相続手続きの種類、期限内に終わらせる方法をご紹介します。 ■不動産相続手続きの期限について 不動産相続の法的手続きである相続税の申告と納税は、亡くなってから10ヶ月以内という期限があります。しかし、これは全ての手続きの期限が10ヶ月というわけではなく、名義変更手続きや相続放棄とで異なります。名義変更の場合は法的な期限はなく、変更の義務も生じません。そのため、行政機関からの名義変更の連絡も来ないことがほとんどです。 相続手続きは、上記でも述べた通り、亡くなったことを知った翌日から10ヶ月間が期限として設けられます。相続内容は、不動産の遺産分割協議や評価額調査を行った上で決めます。期限を超過すると延滞税が発生することがあるので要注意ですが、場合によって、申請期限猶予の申請や、仮申告をして延長が認められるケースもあります。 相続しない場合、相続放棄という形になります。相続人が亡くなったことを知った翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければいけません。この期限を守れなかった場合、相続放棄ができなくなってしまう可能性もあります。申し立てに設けられている期限は3ヶ月しかないので、司法書士や弁護士などに相談するとスムーズに進むでしょう。 ■相続手続きを期限内に終わらせる方法について 遺言書がある場合はそのまま遺言書に従って手続きを進められますが、遺言書がない場合は、まず財産を特定して財産目録を作成しましょう。それをもとに相続人を確定して遺産分割協議を行うのですが、遠方に住んでいる方がいたり、相続同士の都合がつかなかったりする場合は、なかなか手続きが進められないこともあります。この場合、相続手続きに詳しい専門家や銀行に遺産整理を依頼するという選択肢もあります。遺言書がある場合でも、ご遺族と揉め事や相違があった時のために、専門家の方に相談することをお勧めします。 -
平野
家の売却をお考えの方へ!
近々家を売却しようとお考えの方はいらっしゃいませんか?家を売るには事前準備から契約まで数ヶ月かかるので、慎重に進めたいですよね。今回は、失敗を避けるために家の売却をする上でやってはいけないことをご紹介します。初めての方はもちろん、経験済みの方にもお役立ちの情報です。 ■家を売却する際の流れについて 家を売る際は、まず事前準備が必要です。この時、売却条件を整理したり、ローンの残債の確認を行ったり、必要書類を用意したりします。その後不動産会社に査定を依頼して、販売価格が決まります。ここまで約1週間〜4週間かかるのが一般的です。 価格が決まると、次は販売活動です。不動産会社の広報によって購入者を集めますが、その際売主は購入希望者の対応や内覧の準備を行います。無事買主が決定したら、不動産会社を通じて買主からの申込書を受け取って、契約書へのサインや手付金の受領などの売買契約を行います。 売買契約が成立すると、決済が終わり次第物件の引き渡しが行われます。この時は、売買代金の残金を受け取ったり、固定資産税などの精算をしたりするのが一般的です。確定申告では、不動産を売却することによって得た収入を上乗せします。家を売った翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行わなければいけません。 ■家を売却する際の注意点とは? 購入者からの値引き交渉があっても、必ず交渉に応じなければいけないというわけではありません。元々の設定価格が最低価格であれば、これ以上は下げられないという意思表明をしましょう。他に、先に購入者の希望価格を聞く方法もあります。しかし、値引きした方がお得感もあるので売れやすくなるのも事実です。 売買契約書は不動産会社が作成するのが一般的ですが、自分で契約書を確認することは大切です。契約は相当な理由がない限り解約できないので、予め話した契約内容通りに記述されているかどうか、金額に差異はないか、ローンに関する記述は正しいかなど、しっかり目を通しておく必要があります。また、解約金が発生してしまうのでそんな事態は避けたいですよね。 -
平野
家を売る際の流れと注意点について解説
家を売る際の流れについて知りたい」「家を売る際の注意点について知りたい」このようにお考えの方は多いでしょう。家を売却するのであれば、まずは流れと注意点について把握することが大切です。今回は、上記の疑問を解決する情報をお届けします。ぜひ参考にしてみてくださいね。 ■基本的な売却の流れについて まずは、売却の流れについて把握しておきましょう。流れを把握することで、見通しを立てやすくなりますね。 1つ目に、事前準備です。具体的にどのようなことをするのでしょうか。準備しておくことは、売却の希望条件の整理、ローン残債の確認です。また、必要な書類も多いため、準備を忘れないようにしましょう。 2つ目に、査定です。不動産会社に依頼して、査定をしてもらいます。査定の結果から、売却価格を決定します。 ここまでの期間の目安は、1週間から4週間ほどです。 3つ目に、売却活動を行います。不動産会社の広告などを通して、買い手を募集します。この際、売主は、購入を希望する人からの問い合わせに対応したり、内覧の準備をしたりします。内覧時の対応も、売主が行いましょう。 4つ目に、売買契約を結ぶことです。買主が決定したら、この契約を結びます。買主から購入申込書を受け取り、内容に問題がなければ売買契約を結ぶことになります。 5つ目に、決済と引き渡しです。決済完了後に引き渡しを行いましょう。 6つ目に、確定申告です。これは、譲渡所得がある場合が対象です。確定申告も忘れないようにしましょう。 以上が、流れについてでした。 ■家を売る際の注意点について ここまで、流れについて解説しました。イメージが湧いたでしょう。そこで続いては、注意点をご紹介します。 1つ目は、名義人を確認しておくことです。名義人を売主本人に書き換えてからでなければ売却活動は行えません。 2つ目は、むやみなリフォームは避けることです。できるだけ綺麗にしておくほうが売れるのではと考える方もいらっしゃると思いますが、リフォームをするとその分販売価格も高く設定する必要が生じますよね。しかし、中古住宅を購入する方の多くは、できるだけ安く購入して自分好みにリフォームしたいと考えています。そのような人々の需要に応えられるようにするためにも、むやみなリフォームは避けましょう。 以上が、注意点についてでした。